相続人全員揃って協議が成立
相続人全員揃って協議が成立
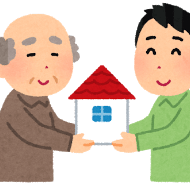 遺産分割を行うにあたって必要となる協議は、相続人全員の同意がなければ成立しません。これは法令で決まっていることであり、亡くなった後に相続人を調べて全員探し出す必要がある理由にもなっています。
遺産分割を行うにあたって必要となる協議は、相続人全員の同意がなければ成立しません。これは法令で決まっていることであり、亡くなった後に相続人を調べて全員探し出す必要がある理由にもなっています。
しかし、亡くなった人の親族の中には、日本国外で生活している場合や消息がわからない場合があります。そのようなときは、該当者の代理となれる者を遺産分割協議に加わらせることで解決させることができます。
例えば、行方不明の者がいる場合は不在者財産管理人を代理にすることができます。不在者財産管理人は家庭裁判所から選任された者が就くことができ、それ以外の者が勝手に不在者財産管理人を名乗っても無効です。
また、遺族に未成年者がいる場合はその人の親権者が代理として協議に参加します。これは未成年者は単独で法律行為をすることが法律では許されていないためです。
もし、遺族の中に疾病などが原因で意思疎通や判断ができない者がいる場合は、成年後見制度を利用してたてた成年後見人が代理者となります。
争族にならないための正しい遺産分割方法とは
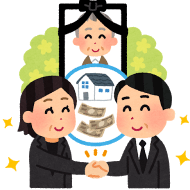 家族といえどもそれぞれ成人していれば別々の生活があり、遺産分割を巡って互いに争うという事も多々あります。
家族といえどもそれぞれ成人していれば別々の生活があり、遺産分割を巡って互いに争うという事も多々あります。
まずは遺産分割協議を行ってその場で相続人全員が納得出来る方法を探すことが、とても重要です。遺産分割には大きくは3つの方法があり、そのどれを採用するといいかは相続人がおかれた状況や条件によって異なります。
基本的には不動産や骨とう品などお金ではない物も含めてお金に価値を換算して、それを公平に分けるのが一般的です。
実際に全てをお金に換えてしまってから分割するというのが、一番分かりやすいし間違いがないでしょう。しかし、相続人のうち誰かが親の面倒を見ているとか同居しているといった事情も考慮して現物を分割せざる得ない事の方が多いものです。
ただそうすると、どうしても価値の相違が出てしまう事があります。こういった場合には、より多くの価値がある物を相続した人が差額分をお金で払うというやり方で解決することも出来ます。
◎2024/2/16
情報を更新しました。
>遺産分割もおいて遺留分侵害額請求が問題になることがあるのか
>遺産分割において物理分割が検討される場面とは
>遺産分割における代償分割の位置づけについて
>遺産分割において換価分割とはどのようなものか
>遺産分割において行方不明者がいるときの手続き
◎2023/4/17
情報を追加しました。
>遺産分割はやり直せるのか気になっている方へ
>遺産分割は住んでいる土地家屋の評価から始めよう
>借地の上に所有権の有る家を建てていたらそれは遺産分割の対象
>遺産分割に期限はないが、相続放棄には制限あり
>遺産分割で土地家屋が未分割になって居る事が日本では多い
◎2022/6/30
情報を追加しました。
>正しい方法で生前に遺産分割を行うことは認められている
>遺産分割トラブルを未然に防ぐ方法と、その後
>遺産分割で異議があるときには専門の法律家に相談するのも1つの手段
>遺産分割協議で揉めないためのペット相続に関する知識
>遺産分割に関連する事柄には時効があるので注意
◎2020/9/11
相続人全員揃って協議が成立
の情報を更新しました。
◎2020/7/14
遺産分割調停のメリットとデメリット
の情報を更新しました。
◎2020/5/15
話し合いをスムーズに行うために
の情報を更新しました。
◎2020/3/16
遺産分割での自動車の分け方
の情報を更新しました。
◎2019/12/17
遺産分割での不動産の分け方
の情報を更新しました。
◎2019/11/29
サイト公開しました
に関連するツイート
